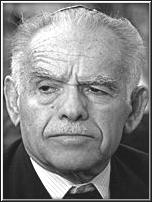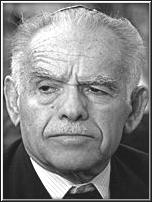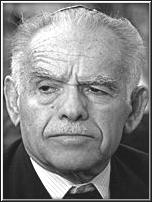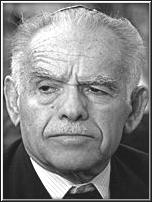(イスラエル:暗黒の源流 ジャボチンスキーとユダヤ・ファシズム 目次に戻る) (アーカイブ目次に戻る)
第9部 近代十字軍 (2008年4月)
小見出し [吊るし上げられたADLフォックスマン] [「近代十字軍」とオスマン帝国] [「青年トルコ」とパルヴスとジャボチンスキー]
[トルコとイスラエル] [欧州へ]
[吊るし上げられたADLフォックスマン]
2007年7月、米国のユダヤ人社会は大揺れに揺れた。ユダヤ・メーソン機関ブナイ・ブリスの幹部で反名誉毀損同盟(ADL)会長として米国社会で比類なき政治力を発揮するエイブラハム・フォックスマンが、米国議会に対して「アルメニア人虐殺問題を取り扱うな」と圧力をかけたからである。
この「アルメニア人虐殺問題」とは、19世紀末ごろから第1次世界大戦にかけてオスマン帝国(トルコ)で数百万人のアルメニア人が殺害されたとされる歴史問題であり、米国を中心として世界に散らばって住むアルメニア人たちはこれを第2次世界大戦中のユダヤ人ホロコーストと並ぶ『組織的・計画的なジェノサイド』として非難・告発し、一方でトルコ政府は『戦時の強制移動中に起こった悲劇』であるとしてその組織性・計画性を否定する。そして米国などのユダヤ人団体の多くは従来から一貫してアルメニア人の側に立って様々な角度から「虐殺問題」を取り扱ってきた。
米国議会はというと、日本に対する「従軍慰安婦問題非難決議」でも分かるように、歴史問題を穿り返しては政治的圧力の道具とすることにことのほか熱心である。もちろんのことだが、自国のベトナム戦争時の虐殺はもとより、イスラエルによるパレスチナ住民虐殺や英国によるインド支配の残虐さに対する非難決議を行ったことは一度も無い。
そして米国議会は一昨年来この「アルメニア人虐殺問題」に対する非難決議を準備してきたわけだが、トルコ政府はこの問題を取り扱わないように米国政府に強く要求し、トルコ中で国民の米国に対する猛烈な抗議と過激なデモが続いた。そして2007年の2月には外相のアブダラー・グルが議会代表者に会い正式にその抗議の意思を伝え、同時にフォックスマンを含む米国ユダヤ人組織に対しても圧力をかけ始めた。
そしてついにフォックスマンはこう語った。「議会の動議がこの件を調停することはできまい。その解決は一つの方向となる。それは判定になってしまう。トルコ人とアルメニア人は彼らの過去の見直しをする必要があるかもしれない。ユダヤ共同体はその歴史の判定者であるべきではなく、米国議会も同様である。」こうしてADLと他の3つの強力なユダヤ組織、米国ユダヤ人委員会、メーソンの国際ブナイ・ブリス、そして国家安全保障問題ユダヤ委員会(JINSA)は、議会にこの問題から遠ざかるように求めたのである。
米国議会がこの一言で「アルメニア人虐殺問題」を取り下げたわけだから、誰が米国の政治を支配しているのか一目でわかろうというものである。しかしそれはさておき、このフォックスマンの発言と米国ユダヤ人組織の態度に対して、米国在住のアルメニア人はもとより、長年彼らと同盟を組んでいたユダヤ人たちが激怒したことは言うまでもない。青年を中心とする大勢のユダヤ人たちがフォックスマンに対して一斉に激しい抗議の声をあげた。しかしこの問題に対して「歴史の判定者」であることを放棄した米国の主要ユダヤ人組織の姿勢は変化しなかった。
どうして彼らは一般のユダヤ人たちが大いに関心を持つこの問題を相手にしなくなったのだろうか? もちろん中東地域でイスラエルとの最も重要な同盟を結ぶトルコを刺激するような愚をおかしたくなかった事情はある。特にその少し前にトルコ議会の総選挙で穏健派とはいえイスラム教政党が政権を取ったことは、イスラエルとシオニストに大きなショックを与えただろう。いまここでトルコがイスラエルにそっぽを向くようなことが起これば、イラン攻撃の機会をうかがうシオニスト政権にとって大打撃となる。ただでさえイスラエルが軍とモサドの要員を送り込んで地歩を固める北部イラクのクルド人地区を巡って軋轢が続いているのだ。
こんなときに歴史問題を穿ってトルコ国民を刺激すればイスラエルにとって致命的な打撃を導くことにもなりかねまい。シオニスト機関として何としてもこのような事態は回避しなければならない事情があったことに間違いは無い。
しかし、この「アルメニア人虐殺問題」の背後には、おそらくイスラエル誕生を巡る、はるかに根深い「歴史問題」が横たわっている。ひょっとするとフォックスマンは表面的・現実的な案件に対してだけではなく、近代史の深奥にひそむ問題が表ざたになるようなことを恐れたのかもしれない。
【以上、参照資料】
http://www.jewcy.com/feature/2007-07-09/fire_foxman
[「近代十字軍」とオスマン帝国]
2001年9月11日の「同時多発テロ」後に、米国大統領ジョージ・W.ブッシュは「十字軍」を口にした。しかし19世紀後半以後の世界史を教科書的な視点から離れて眺めなおしてみるならば、この「十字軍」は大英帝国によるオスマン帝国転覆・解体謀略から本格的にスタートしたように思える。「アルメニア人虐殺問題」は単なる民族紛争ではない。それはまさしくこの「近代の十字軍」による中東制圧支配計画の中で起こった出来事であるに違いない。
現在のトルコ東部にあるアナトリア地方では何百年もの間イスラム教徒であるトルコ人とキリスト教徒であるアルメニア人が平和共存してきた。イスラム教徒たちはどこでも他の宗教を禁圧する道を選ばなかったのだ。たとえばイベリア半島では彼らは数百年間にわたってキリスト教徒やユダヤ教徒と共存してきた。イスラム教徒はその「姉妹宗教」を攻撃せず支配地域を「一色に塗りつぶす」ことをしなかった。それを行ったのはイスラム帝国滅亡後のキリスト教徒たちであった。
大英帝国のみならず支配者たらんとする者にとって「支配するためには分割せよ」は鉄則である。英国や米国が地政学的にも資源確保にとっても世界の最重要地域である中東地域を支配するために用いた手段も例外ではない。彼らはオスマン帝国支配地域に住むキリスト教徒たちに手を差し伸べ援助し、彼らに帝国内での経済的・社会的高位を確保させた。アルメニア人がその最大のターゲットになったことは言うまでもない。次第に長年平和裏に共存してきたイスラム教徒のトルコ人たちと彼らとの間に亀裂が生じ多くの反感が生まれたことは当然に帰結である。しかしそれでもトルコ人たちはアルメニア人との共存の意思を捨てなかったし、アルメニア人たちもオスマン帝国から自分達を切り離そうとはしなかった。
オスマン帝国の解体を目論んだのは大英帝国ばかりでなく北方の巨人ロシアも同様であった。ロシアは積極的にロシア在住のアルメニア人をオスマン帝国に送り込み、民衆を扇動し暴動を組織するようになった。それはロシア帝国内のイスラム教徒たちに対する弾圧と軌を一にしたものだった。彼らは1890年代からオスマン帝国内に武器を密輸し過激なアルメニア民族主義を焚き付け武力による「革命」を叫んでオスマン帝国を内部から崩しにかかった。この時点でアルメニア人の存在はオスマン帝国にとって非常に危険なものになり始めたのである。
特に大活躍したのはマルクス主義者たちである。主要なグループが二つあり、一つは1887年にスイスのジュネーブで結成されたフンチャック(Hunchak)と呼ばれるフンチャキアン(Hunchakian)革命党、他はダシュナック(Dashnak)と呼ばれるアルメニア革命会議である。後者は1890年に結成されロシアに資金援助を受けていた。彼らはイスラム教徒との共存を維持しようとする教会の神父たちや商人達を次々と殺害し、アルメニア人を反イスラム、反オスマンに囲い込んでいった。経済破綻と政治腐敗に苦しむオスマン帝国と一般のトルコ民衆にとってアルメニア人の存在がどのようなものであったのか、容易に想像がつくだろう。
しかし、アルメニア人たちの弱点は、その最も密集した居住地域においてさえも人口の20%を超えないという分散した状態であった。扇動家たちの動きが活発になればなるほど一般のアルメニア人民衆におよぶ危険が飛躍的に大きくなったのは当然のことである。悲劇は始めから予想されたことだった。
繰り返すが、これらの全ては欧米国家を支配する者たちがこのイスラム帝国解体のために仕組んだ策略だったのだ。彼らにとってアルメニア人は一つの「コマ」に過ぎなかったのである。この点は第1次大戦中に大英帝国のスパイであるロレンスに扇動されたアラブ人たちも同様であった。そしてついにオスマン帝国では内患外憂のなかで劇的な体制変革が行われることとなる。
【以上、参照資料】
http://homepages.cae.wisc.edu/~dwilson/Armenia/justin.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide
[「青年トルコ」とパルヴスとジャボチンスキー]
1908年に起こった「青年トルコ人革命」は「統一と進歩委員会」に主導される政治運動であり、1878年にわずか2年足らずで効力を停止させられた憲法とそれに基づく政治の復活を叫んで、スルタン・アブデュルハミト2世を追放した政治変革であった。この「統一と進歩委員会」は「青年トルコ党」と訳されることもある。しかしこの政変を起こした「青年トルコ運動」は多くの集団の動きから成り立っており「統一と進歩委員会」がその最大党派であった。オスマン帝国を掌握した「青年トルコ運動」は次第に過激な民族主義の色彩を帯びるようになり、第1次世界大戦中に「アルメニア人大虐殺」を実行したのも彼らの政府であった。
不思議なことにこの「青年トルコ運動」は決して人種的な意味のトルコ人だけで成り立っていたものではなく、オスマン帝国内のさまざまな民族の出身者が参加していた。彼らの多くは英国などに留学して近代の西欧から多くの近代化に関する手法を十分に学んだ者達であった。しかしそれだけではなかったようである。
ここに不思議な人物がいる。名はアレクサンダー・パルヴス。本名はイスラエル・ゲルファンドで、英語読みでは普通ヘルファンドと呼ばれる。ロシア生まれのユダヤ人で、日本ではあまり知られていないようだが、レオン・トロツキーらとともにマルクス主義者としてロシア革命を推進した中心的な人物の一人である。そしてそのパルヴスはこの「青年トルコ人革命」の期間に5年間イスタンブールに滞在し、この間にそこを拠点としてバルカン半島の紛争に対する武器商人として暗躍し相当な収益を手にした。そして彼は「青年トルコ運動」のパトロンの一人となり同時に政治アドバイザーともなった。
しかし奇妙な話である。彼は武器の製造と販売でドイツのクルップ財団と手を組み、さらに英国から「サー」の称号を受け取った悪名高いギリシャ系武器商人ベイシル・ザハロフが経営するヴィッカーズ株式会社(英国)のビジネス・パートナーでもあった。そしてその一方で彼は共産主義者としてロシア革命を導き、同時に「青年トルコ運動」を支えていたのである。このパルヴスを英国諜報機関のエージェントと見なす人もいるがそのように思われても無理からぬ面を持っているのだ。
そして同じイスタンブールにもう一人の奇妙なユダヤ人の姿を認めることができる。ウラジミール・ジャボチンスキー。彼は一般的にパルヴスとは逆に反共主義者だったとみなされるが、トルコでの動きは一致している。ジャボチンスキーは「青年トルコ革命」直後にイスタンブールに到着し、すぐに新聞「青年トルコ」の編集長となった。
リンドン・ラルーシュとその運動の歴史家によれば、この新聞は当時のトルコ政府の閣僚にいた人物によって所有されていたが、立ち上げたのはロシアのシオニスト団体、そしてブナイ・ブリスによって運営され、その編集はシオニストでオランダ王家の銀行家であるジャコブ・カーンによって監督されていたという。イスラエル「建国の祖」の一人であるジャボチンスキーはまずトルコの政治改革に関わっていたのである。
共産主義者であるパルヴスと反共主義のシオニストであるジャボチンスキーの両方がこのときにトルコにいた。そしてその一方で同じ共産主義者たちがアルメニア人を自殺行為にも等しい過激民族主義運動に駆り立てていたのだ。その背後には西欧支配者とそれに連なるシオニストの姿が見え隠れする。そしてアルメニア人たちは「青年トルコ」政府による強制移住と弾圧の後に米国など世界各地に散らばり、現在アナトリア地方にはほとんど住んでいない。文字通り「国無き民」となってしまった。
その後オスマン帝国にとってまさに《自殺》としか言いようのない第1次世界大戦参加を経て、小アジアに限定された国家のすべてを西欧化した「トルコ建国の父」ムスタファ・ケマル・アタテュルクを初代大統領とする「欧州の一部」トルコ共和国が誕生する。このアタテュルクは当然のごとくこの「青年トルコ運動」に参加してきた人物だった。この運動が、西欧勢力がオスマン・イスラム帝国に放った《最後の刺客》であったことに疑いの余地はない。
そしてその帝国から「解放すべき」パレスチナの土地を巡って、ロスチャイルド卿と英国外相バルフォアとの間で密約が結ばれたことが「イスラエル建国」の直接の開始を告げるものであった。そこにシオニストおよびユダヤ人組織と縁の深い共産主義運動が絡んでいたことに何の不思議もあるまい。現代のシオニスト・イスラエルとトルコ共和国との関係はすでにこの当時から根を植えつけられていたわけである。イスラム帝国を解体して生まれたトルコ「欧州」共和国と、そしてその同じプロセスで源流が作られ、ソ連、ドイツ、英国、米国の総力を挙げての中東イスラム国家破壊工作の結果として誕生したシオニスト・イスラエルは、元々からの「シャム双生児国家」だったといえるだろう。
【以上、参照資料】
http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Helphand
http://www.schillerinstitute.org/conf-iclc/1990s/conf_feb_1994_brewda.html
[トルコとイスラエル]
ロシアのシオニストといえば、ジャボチンスキーのほかに、「シオン労働者(Poalei
Zion)」党を率いたベル・ボロチョフやその党員で「ボルシェヴィキ」であったダヴィッド・ベン-グリオンなどが有名だが、同じ共産主義者のパルヴスがシオニストであったのかどうかは分からない。トロツキーとともに「永久革命論」を唱えて欧米のユダヤ組織から革命資金を集めていたパルヴスは、シオニズムの外側でそれを動かすもっと大きな勢力につながっていたのかもしれない。彼が英国ヴィッカーズのみならず後にナチスのパトロンとなるクルップ財団とのつながりを持ち、英国のエージェントとして動いていた可能性は十分にあるだろう。いずれにせよ西欧支配者念願のオスマン帝国つぶしと属領化に一役買ったことに間違いは無い。
なおそのパルヴスだが、同じユダヤ人であるローザ・ルクセンブルグの率いたドイツ革命を支持し、革命失敗後にはワイマール共和国を拒否した。にもかかわらず彼は特に処罰されるわけでもなく、逆にベルリンに程近いところに豪勢な住宅を与えられて隠棲生活を送り、1924年に57歳で死亡した。
そして一方のジャボチンスキーはパレスチナに渡って後のイスラエル国防軍となるハガナーを創設した。その後1923年に「鉄の壁」を著してシオニスト主流派と分かれ、東欧を中心にベタールを組織し、ムッソリーニの協力を得てそれをイタリアに広げ、そして1940年に米国でベタールを創設する最中に死亡した。これは今までの回で申し上げたとおりである。
この二人の共通点といえば、どちらもオデッサ生まれのユダヤ人であり、若いころにスイスで学んだことである。しかし彼らが接触を持った形跡は無い。パルヴスはジュネーブでマルクス主義を学び、ジャボチンスキーはすぐにイタリアに渡ってマッツィーニ風の過激な民族主義を学んで後にそれをシオニズムに導入した。しかしスイスといえば、例の過激なアルメニア民族主義運動を率いたフンチャックもジュネーブで結成されたし、第1回シオニスト会議が開かれたのは1897年のバーゼル、第1インターナショナルも1866年にジュネーブで最初の集まりを持った。そのほかにもナチス幹部の米大陸への救出など、この国は様々な国際的な秘密活動や謀略的活動の本拠地となってきた。
さらにラルーシュによれば、ジャボチンスキーもパルヴスも、ともにロシア帝国末期の悪名高い秘密警察オカラナの幹部であるセルゲイ・ツバトフに見出され抜擢されたということだ。そしてそのツバトフこそ大英帝国とシオニストの密偵であったそうだ。しかしその点の詮索は止めておこう。我々はもう一度、トルコとイスラエルの関係に戻らなければならない。
地理的な位置から見て、明らかにトルコは欧州と中東を結ぶ最重要拠点である。「聖なるマフィア:オプス・デイの素顔を暴く
」シリーズにも書かれたことだが、いまだに「ヒトラーの教皇」と呼ばれ続けるピオ12世の下で、バチカンのギリシャ・トルコ大使として派遣されたアンジェロ・ジュゼッペ・ロンカッリ(後のヨハネス23世)は、ユダヤ人たちの一部を東欧からパレスチナに移送するために獅子奮迅の活躍をした。ヒトラーとピオ12世は悪役、このロンカッリは善玉を演じてはいるが、要は一方が「追い立て役」であり他方が「運び役」であっただけだ。そして当のパレスチナにはヒトラーとのハーヴァラ協定以来受け入れ態勢を整備しつつあったスターリニストたちが「選ばれたユダヤ人」たちの到着を待っていたのである。
イスラエル建国にとって、欧州と中東の橋渡しの位置にあるトルコ共和国が持つ重要性は測り知れない。トルコが、いまだに国民の大多数を占めるイスラム教徒の反対を押さえつけて、イスラエル成立後に一貫してその存在を支持し軍事同盟すら締結していることは言うまでもあるまい。この2国は始めから「姉妹」として作られた。当然のことながら軍事的には「欧州の一員」としてNATOに組み込まれ、スポーツなどの文化面ではイスラエルとともにすでに「欧州」である。両国は欧州が「近代十字軍第一次攻撃」の結果として中東に打ち込んだ「クサビ」なのだ。
現在、軍事的な同盟だけではなく、イスラエルにとってトルコは国家の存亡を左右するものとなっている。カスピ海沿岸の石油と天然ガスを運ぶパイプラインはもとよりトルコからイスラエルへの水輸送パイプが計画されている以上、もしトルコが反米反イスラエルの姿勢を明確にするなら、このシオニスト国家の命脈もそれで断ち切られてしまうだろう。イスラエルとしては他のあらゆる問題を棚上げにしてでもトルコ(穏健イスラム)政権を刺激してはならない。フォックスマンが米国の多くのユダヤ人の反発と指弾を覚悟してでも「アルメニア人虐殺問題」に蓋をせざるを得ないわけである。
またトルコの動向は米国とイスラエルの支配層が画策するイラン攻撃の成否を左右するものになるだろう。さらにはクルド人地域に対する攻撃によってイラク分割計画にも重大な影響を及ぼしかねない。さらに言えば、一応は19世紀後半以来の計略が成功し西欧型の世俗主義政権が確立しているとはいえ、やはりこの国の基盤はイスラム教徒なのだ。同様に世俗主義であったイラクのフセイン政権がイスラエルと米国のシオニストによって打ち倒され事実上の国土分割が行われていることを、トルコ国民がどんな複雑な思いで見ているだろうか。この100年以上にわたって「近代の十字軍」を押し進めている者達が、パレスチナやイラクのみならず、将来において再びトルコ国内に「線引き」を行わないという保証はどこにもないのだ。何百年間にもわたって中東の大帝国を築き上げてきたこの国の国民は決して馬鹿ではない。何が彼らを翻弄してきたのか十分に知っている。
そのようなときにこの「アルメニア人虐殺問題」はあらゆるレベルで最もデリケートなテーマとなる。それは西欧支配層による世界各地の分割・転覆・支配策謀の歴史の中で最も際立った残虐性を帯びるものの一つだからである。19世紀後半に、国際共産主義運動とほぼ同時期に現れ出たシオニズム運動もまた、単にユダヤ人の内部から自発的に生まれ出たものとは考えにくい。オスマン・イスラム帝国は「近代十字軍」の最初の餌食となった。その解体と再編成に共産主義とシオニズムの両方が関与している。そして文字通りの「国無き民」アルメニア人こそがその最大の犠牲者なのだろう。彼らは告発すべき者を誤っていたのかもしれないのだが、今回のシオニストたちの態度をきっかけに「虐殺」の真相に気付くことを期待したいものである。
【以上、参照資料】
http://larouchein2004.net/pages/interviews/2002/020605yarin.htm
[欧州へ]
トルコの情勢は将来EUにこの国を迎える可能性を持つ欧州にとってもまた重大な関心事とならざるを得ないのだが、現在のところ米国同様にどの国も「触らぬ神に祟りなし」を貫いているようだ。それどころか、ひところ盛んだった「反イラン・キャンペーン」も鳴りを潜めている。そのかわり現在各国国民の関心は中国に向けさせられており「中国のアルメニア」たるチベットを巡っての反北京キャンペーンが繰り広げられている。これがオリンピック絡みの汚染問題や食品衛生問題などに対する北京政府の無策ぶりと重なって、大きな「反中国ブーム」が作られつつある。
そして現在その流れと並行しその陰に隠れるように、特に英国、フランス、オランダ、北欧諸国、イタリアで、シオニスト勢力が着々とその支配の輪を固めつつある。英国ではネオコン子飼いのブレアーが去ってもやはり事情は一向に変わらないばかりか、国内のイスラム教徒に対する締め付けは厳しくなりつつある。フランスではサルコジ政権の登場以来、政治的にも文化的(マスコミ報道や出版など)にも親イスラエルの流れが強化されつつある。欧州各国国民は欧州の「米国化」に対して非常に強い抵抗感を抱いている。しかしそれを突き崩し、極少数派のシオニスト組織が全面支配する米国型システムとイスラモフォビア(イスラム嫌悪)が、一般の欧州人と欧州に多く在住するイスラム教徒との亀裂を徐々に生み出し一般社会を様々に揺り動かしながら、一歩一歩着実に侵入してきているのだ。
しかしその点の話は次回に回すことにしたい。欧州で始まったシオニズムは将来の何かの「巨大なショック」をきっかけにして新たなファシズムとして欧州を席巻することになるのだろうか。2001年以降の米国のように。
(イスラエル:暗黒の源流 ジャボチンスキーとユダヤ・ファシズム 目次に戻る) (アーカイブ目次に戻る)
第10部 近代欧州史の深奥 (2008年7月)
小見出し [再度、なぜトルコなのか?] [偽預言者の系譜] [重層社会としての欧州] [シオニズムとは?]
[再度、なぜトルコなのか?]
イスラエルの中東支配に大きな鍵を握るのがトルコであることは前回申し上げたとおりなのだが、しかし奇妙である。オスマン帝国末期にいきなりシオニスト・ユダヤ人がトルコに登場して活躍を始めたとは思えない。それだけの活動を行うためには、その活動を支える根強い何らかの潮流が以前から作られていなければならない。オスマン帝国とシオニズム以前のユダヤ人社会の間に、いったいどんなパイプが作られていたのだろうか。
サバタイ・ゼヴィ(Sabbatai
Zevi;Shabbethai、Zvi、Tzviなど様々に表記される)といっても、よほどユダヤ史を研究している人以外には、ご存知の方はほとんどいないだろう。しかしユダヤ人の間では「自称メシア」つまり「偽メシア」として有名な人物である。彼は1626年にトルコのスミマにあるユダヤ共同体の中で生まれた。若いころは神秘主義とカバラ魔術に凝ったと言われるが、やがて17世紀に英国で発生した千年王国思想に影響を受け自らを「メシア」と名乗るようになる。
なお、この英国で流行した奇妙な思想だが、新約聖書のヨハネの黙示録に出てくる「666」という偽キリストの数字から「1666年が終末の年であり、そこからキリストが支配する千年王国が始まる」という他愛の無いもので、もちろん1666には何も起きなかった。しかしその流行の周辺を眺めてみるならばとても「他愛の無い」などといえた代物ではない。まずオリバー・クロムエルなどの英国清教徒が率先してこの思想を高唱した。そしてポルトガルのラビであるメナッセー・ベン・イスラエルはユダヤ人のメシア待望、「イスラエルの失われた十支族」が英国に住み着いたというデマ、十字軍以来のキリスト教徒のシオン願望、そしてこの千年王国思想を巧みに利用しながら、クロムエルと英国議会を説得し、英国のキリスト教徒がオランダとポルトガルに住んでいたユダヤ人を受け入れるように導いた。こうして英国でキリスト教ともユダヤ教ともつかぬ奇妙なメシア思想が根付いていった。
ちなみにいうなら、後にアメリカ大陸に移りそこを「神に約束された聖なる地(=シオン)」に見立てた清教徒たちの源流はこのあたりにあるのだろう。もともとユダヤ教の影響を受けるカルヴァンの流れなのだが、米国のキリスト教は、欧州のそれとはかなり異なった様相を示していること、原住民を大量虐殺しながら自らの国土を造っていった歴史が旧約聖書の記述に類似していることなどをみても、それは最初から純然たるキリスト教とは言いがたい面を持っている。
ゼヴィの父親はオスマン帝国の英国代表部のエージェントとして働いていたのだが、元々神秘思想にかぶれたゼヴィがこの潮流に目をつけないはずはない。彼はわずか20歳のときにすでにスミマで「イスラエル王国を再建すべく神に選ばれたメシア」として名乗りを上げていたのだ。イスラエル王国を再建? そして「メシア」に成りすました彼は小アジア〜東欧各地のユダヤ共同体の中で歴史的に「サバティアン」と呼ばれるようになる信奉者を増やしていく。
彼の主張の際立った特徴は反道徳主義であろう。すでにこの世にメシアが登場したからにはもはや人間から罪は消えた、ゼヴィに従う限り何をしてもそれは罪として数えられない。恐ろしい発想だがこれは何もゼヴィが発明したものではないしユダヤ教起源のものでもない。キリスト教にも仏教にも同様の傾向は存在する。しかしゼヴィの場合は際立っていた。彼は1666年にオスマン当局に弾圧されそうになるとイスラム教に改宗しアジズ・メヘメットと名乗った。それをユダヤ教徒から非難されると「イスラム教徒をユダヤ教に改宗させる方便だ」と答えたのだが、一方でオスマン帝国のスルタンに対しては「ユダヤ教徒をイスラム教徒に改宗させる」と語ってその関係を維持し、イスラム教徒の間にもそのセクトを広げた。
彼とその信奉者たちにとって奪うことや殺すことはもとより、二枚舌を用いて騙すことは何一つ罪にはあたらない。こうして彼らの間から道徳と法を規定する唯一絶対の神は消えた。ゼヴィは1676年にモンテネグロで死亡したが、「イスラエル王国を再建すべく神に選ばれたメシア」の思想的影響は強烈に東欧と小アジアのユダヤ人たちの間に根付いていったのである。ここで注意深い読者なら、このような発想が現在のシオニストのそれに瓜二つであることにハッとさせられるかもしれない。
信心深い旧来のユダヤ人の中にシオニストたちを「偽メシア」と呼ぶ人たちがいる。彼らがこのサバタイ・ゼヴィを意識しているのは明らかであり、その潮流の中にシオニズムの起源を見出しているのだろう。そしてこの堕落し果てた偽メシアのユダヤ人がこの時代にすでに英国とトルコとユダヤ社会の間をつないでいたことを忘れてはならない。彼は「イスラエル王国再建」のためにトルコを利用しようとした。ゼヴィの父親が仕えた英国がその動きを掌握していなかったはずもあるまい。19世紀末に登場する新たな「偽メシア」はこのような土台のうえに活動を開始したのである。前回お知らせしたアルメニア人虐殺を実行した「青年トルコ運動」の主力にこのサバティアン・セクトの末裔が多数含まれていた。
【以上、参照資料】
http://en.wikipedia.org/wiki/Shabbatai_Zevi
http://www.kheper.net/topics/Kabbalah/antinomian.htm
http://www.rense.com/general64/zzzio.htm
[偽預言者の系譜]
この極めて人間的な劣悪で危険な思想が相当な数の人間に影響を与え思考を狂わせ続けていくだろうことに疑念の余地はあるまい。東欧のユダヤ人内部でじきに新たな「メシア」が登場することになる。ジャコブ・フランク(1726-1791)である。彼はサバタイ・ゼヴィおよびダビデ王の生まれ変わりを自称し、東欧から西欧一帯のユダヤ人社会に大きな影響を与えた。当時彼らは、東欧各地で王侯貴族の庇護の元に経済と小工業生産や流通を取り仕切り、各地域の中で大きな政治的影響力を誇っていた。
フランクは当時ポーランド領であったウクライナで生まれたといわれるが、父親はやはりサバティアンであった。当時のポーランドには数多くのサバティアンの秘密組織が存在したのである。当然だが伝統的なユダヤ教ラビたちはサバティアンを厳しく禁じ取り締まった。しかしその人間の悪徳と貪欲と狂信を一身に集めたこのメシア思想が簡単に消えて無くなるわけもない。中流クラスのユダヤ人たちの多くが徐々にこの悪魔的思考「フランキズム」に取り付かれていく。
フランクとその支持者達はポーランドの伝統的ラビたちから危険視され何度もそこを追い出されるのだが、彼らはタルムードを捨てカバラとゾハールを信奉し、そして非常に奇妙なことに、それがキリスト教の神秘思想である「三位一体」の考えと矛盾しないことを主張した。
思想的に言えば、強烈なメシア主義とともに、やはりフランキズムの反道徳主義を指摘する人が多い。サバティアンの中から出てきた以上当然のことなのだが、善と悪の概念を区別しない、あるいは都合に従ってその名目上の境目を消したり動かしたりできるのである。もちろん自ら「メシア」を名乗る者の都合である。欺くこと、破壊すること、殺すことの全てがその都合に従って「悪」から「正義」へと移項されるのだ。
彼がゼヴィの後継者であると名乗り始めてから、ちょうどこの大先輩がオスマン帝国に取り入り二枚舌の改宗を行ったのと同様に、ローマカトリックに近寄り洗礼まで受けてしまった。1759年の話である。その後、フランクに率いられるサバティアン系統の中流クラスのユダヤ人たちが続々と彼に倣った。同時にそのかなりの部分がプロテスタントにも「改宗」することになる。このようにしてキリスト教に浸透したユダヤ人たちはその中でそれぞれの宗派の伝統的精神を腐らせていくことになるのだ。なぜなら、彼らがカトリックやプロテスタントの信徒でありながら同時にフランクやゼヴィのメシア思想に従うことができたからである。彼らに道徳は無い。どこにいてもその信仰、思想、信条を変えないままにフランクの使徒たりえたのだ。
伝統的なユダヤ人たちは、現在でもそうだが、彼らを「フランキスト」と呼んで軽蔑し警戒した。しかしこの流れもまた、現在のキリスト教シオニスト、カトリック・シオニストの大流行を考える上に大きなヒントとなるだろう。これらは決して100年やそこら続いた程度の動きではないのだ。
ジャコブはその後ローマから疎んじられポーランド当局に逮捕されたりもするが、ドイツに移り住みフランクフルトを経てオッフェンバックで豪勢な生活を送った末に、娘を後継者に指名して1791年に死亡した。彼の重要なパトロンが後にロンドンとパリを支配することになるフランクフルトのロスチャイルド家でありその周辺にイエズス会のアダム・ワインハウプトがいたことは説明の必要もないだろう。
彼の言動の中で注目すべきことがある。彼はカトリック教会に対しては「ユダヤ教は旧約聖書にあるヤコブでありカトリックはエソウである(旧約聖書ではヤコブは弟のエソウを騙して殺しそれを知った神はヤコブをエデンの東に追放したとされる)。いまやヤコブとエソウの仲直りのときが来ている」と語り、その一方で自分の支持者に対しては「聖書にあるヤコブのようにキリスト教徒を騙してパレスチナの地に反キリストの王国を建設するのだ」と、大先輩に習って二枚舌を弄した。パレスチナの地に反キリストの王国? まさに現代イスラエルのイメージそのものではないのか?
彼の支持者の中にはキリスト教とは逆に啓蒙思想に走り、フランス革命を支持しあるいは積極的に参加した者も多くいた。フランス革命が新興ブルジョアジーの革命でありその中にユダヤ人中産階級が多く含まれている以上当然のことといえる。ジャコブ・フランクをむしろ「ユダヤ人に啓蒙思想をもたらした人物」として、さらには「近代世俗思想とフェミニズム」そして「シオニズムをもたらした人物」として紹介する者も多い。こうして彼らはカトリック、プロテスタント、そして世俗主義のそれぞれの内部で強力なグループを作り、西欧から東欧、北欧からトルコ、そして北米大陸にいたる主要な世界の隅々にまで浸透していくこととなるのだ。
《注記:この点についてはひょっとすると、19世紀末から20世紀初期にかけて、カトリック内部で起こっていた「シヨン運動」とのつながりがあるのかもしれない。こちらの「聖なるマフィア オプス・デイ」の「第7部:十字架とダビデの星」にある[シヨン運動と第2バチカン公会議]を参照のこと。》
特に啓蒙思想に流れた者達の動きは巨大である。それはアメリカ革命(独立)、フランス革命、トルコ革命、そしてロシア革命に至る近代の革命にとって原動力の一つとなっている。このような革命思想が全てある種の「世俗的メシア思想」であることに注目しなければならない。そして・・・、その「世俗的メシア思想」の中にシオニズムもまた含まれている。それは近代ユダヤ人社会の中で脈々と受け継がれるサバティアンの流れから登場して来たのである。ここでも東欧とトルコが鍵を握っているのだ。
社会主義者で左派シオニストと一般的に呼ばれるダヴィッド・ベン・グリオン、モシェ・シャレット、イツチャック・ベン・ズヴィなどがイスタンブールに住みそこで学び(ベン・グリオンはロシア国籍を捨ててオットマン帝国の国籍を得ていた)、共産主義者アレクサンダー・パルヴスが「青年トルコ革命」を援助し、ファシストであるウラジミール・ジャボチンスキーが革命運動機関紙の編集長を務めたことなど、何一つ不思議には当たらないのである。
【以上、参照資料】
http://www.kheper.net/topics/Kabbalah/antinomian.htm
http://www.rense.com/general64/zzzio.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Frank
http://www.aranpa.com/smoked%20glass.htm
http://www.rense.com/general49/hhee.htm
[重層社会としての欧州]
どうしても我々は国境を元にして世界地図を垂直方向に切って考えてしまう癖が付けられている。これは日本が孤立した島国であることの影響もあるだろうが、主要にはむしろそのような学校教育の結果だろう。実際には地面にへばりつくように生きる下々の者達以外にとって、国境など存在しないのである。超国家組織とそれが伸ばす網の目は、陸続きの欧州では数百年、千数百年も昔から当たり前なのだ。
その典型的な例がローマ教会であり王族や貴族による「高貴なる血(青い血)のネットワーク」である。またローマ教会がラテン語という共通言語によってその支配の網を維持したのだが、その上に乗って近代の科学者や哲学者のネットワークが形作られた。さらにはその科学者集団の原形である錬金術師、そしてフリーメーソンの起源であろうといわれる建築家たちの動きにも国境など存在しなかった。
その国境の無い人と富と思想の流れの中にユダヤ人グループのそれがあったことは言うまでもない。15世紀末にスペインを追放されたセファラディ・ユダヤも、それ以前にハザールの滅亡によって東欧に散ったアシュケナジ・ユダヤも、常に各地の王侯貴族の下でその経済を支える同時に共同体同士で常にオープンな通路を保っていた。
国境線によって垂直に区切られた世界認識では、このような実際の欧州の姿、そして現在の世界の姿は見えてこない。さらには今まで述べたように、それぞれの超国家集団の間に相互の浸透があり、やがて一方が片方を支配するようなこともあるだろう。これは何か特別な陰謀などではない。重層社会としての欧州では至極当たり前のことに過ぎないのである。
サバタイ・ゼヴィ、ヤコブ・フランクといった、人間の持つ権力への願望と劣情と狂気を最大限に引き出す文字通りの「偽メシア」の思想は、ユダヤ人社会が昔から持っていた通路を通って一気に欧州と小アジアに広まり、それがイスラム教とキリスト教、そして世俗主義の中に根深く浸透していった。それはあたかも血管を伝わって広がった毒が体の様々な組織の中に染み込み体中の細胞を犯していくように、欧州と北米の社会をガンジガラメにしていくのである。
そしてそれは最初から「パレスチナのイスラエル王国再建」を目指すものであった。根っからの無神論者であるダヴィット・ベン・グリオンやゴルダ・メイヤなどがパレスチナを「約束の地」と語る心情に決して嘘はあるまい。彼らは、2000年前にパレスチナを追われたユダヤ人の系譜ではなく、この偽メシアの系譜に属しているのである。「パレスチナ人などはいなかった」とうそぶくメイアの姿は、まさにサバティアンとフランキストの反道徳主義をそのまま語っただけである。最も大切な同盟国アメリカの軍艦を襲撃して皆殺しにしようとしたシオニスト・イスラエルの姿、パレスチナ人に対するアパルトヘイトと虐殺の政策、そして虚構と脅しで米国人を見張り資産を巻き上げる米国シオニストの姿、アルメニア人を騙して扇動し数十万人を殺したサバティアンの子孫の姿、チェカとNKVDを主導して数百万のロシア人を虐殺したユダヤ人共産主義者の姿、さらには無数のユダヤ人同胞を未曽有の苦難に放り込み見殺しにした
シオニストたちの姿、…、これらはすべてこの偽メシアの系譜に属している。
19世紀後半に盛んになった反ユダヤ主義に対する反応として生まれたシオニズムなどといった、特に左翼が好みたがる通説が、いかに上っ面だけの真相を覆い隠すたわごとに過ぎないのかは明白であろう。
【以上、参照資料】
http://www.rense.com/general64/zzzio.htm
http://www.isreview.org/issues/04/zionism_false_messiah.shtml
http://www.rense.com/general49/hhee.htm
[シオニズムとは?]
自ら「陰謀論者」を名乗る不思議な「反ユダヤ主義ユダヤ人」ヘンリー・マコウは、いわゆる「ユダヤの陰謀」およびシオニズムの本体を大英帝国主義の中に見ている。当然だがその大英帝国の中枢部はロスチャイルドを筆頭とするユダヤ系資本に握られる。しかしロスチャイルドの到着以前にも、大英帝国の基礎固めの時期である16〜17世紀にはオランダやポルトガルから大量のユダヤ人が英国に移り住み支配階級の間に強力なネットワークを築き上げていた。遅れてフランクフルトからやってきたロスチャイルド家はその土台なかで頭角を現した。
《注記:これらの点に関するヘンリー・マコウの主張は『「ユダヤの陰謀」の正体は大英帝国主義である』および『シオニズム:ユダヤ人に対する陰謀』をご覧いただきたい》
そしてそのロスチャイルド家がジャコブ・フランク最大のパトロンであった。英国が近代シオニズム発祥の地であったとしても何の不思議も無いのだ。大英帝国はそのスパイ網を東欧・ロシアから中東一帯に張り巡らせていたのだが、オスマン帝国内でのトルコ革命やロシア革命がユダヤ人主導の元に行われたと同時に、それらを大英帝国のスパイ網が逐一キャッチしコントロールしていたことに疑念の余地はあるまい。欧州の重層社会と水平に広がる様々なネットワークを知る者にとってはほとんど常識の部類であろう。
マコウもその一人なのだが、敬虔で真面目なユダヤ人、正義感と道徳観に溢れたユダヤ人の中には、シオニスト(サバティアン、フランキスト)こそが反ユダヤ主義を必要としており反ユダヤ主義の源泉の一つであると見る人が多い。19世紀後半からロシアに吹き荒れたポグロムの嵐やドレフュス事件などを最も上手に利用したのがシオニストであったことは誰の目にも明白である。
あのウラジミール・ジャボチンスキーが、9百回に近いポグロムを指導しおよそ3千名のユダヤ人を虐殺したシモン・ペティルラと同盟工作を行ったことにも別に何の不思議もあるまい。彼を単なる「ユダヤ人の裏切り者」と見なすのは片手落ちであろう。彼が17世紀以来の「偽メシアの系譜」につながっていると仮定すればすべての筋が通る。この系譜は東欧を中心にしてすでに強力なネットワークを築き上げていた。彼らにとって道徳などは存在しないのだ。道徳の存在しないところに裏切りなどは無い。全てが正当な行為に過ぎないのである。現実が狂気を産み出すと同時に、狂気が現実を生み出すこともありうることを忘れてはなるまい。
そしてその「偽メシアの系譜」はパレスチナにイスラエル王国を再建することに照準を絞る。しかしそんなちっぽけな願望でこのような狂気が産みだされるのだろうか。ここでこの偽メシアの思想がキリスト教の中から生まれた千年王国の思想と合体していることを思い起こす必要があろう。彼らにとってイスラエル王国の再建は、そのまま世界の絶対的支配につながる重要なステップなのだ。馬鹿馬鹿しいと思わずにヨハネの黙示録をめくってみていただきたい。
おそらく20世紀のイスラエル建国はその一つのステップであり、イスラエルの建国とその維持のみに絞った狭い意味のシオニズムは単なる方便に過ぎまい。シオニストの働きは世界的なものである。日本でさえすでにガンジガラメにされている。英国はもとより、フランスではサルコジのシオニスト政権がすでに誕生しており、ドイツのメルケル政権は完全にシオニストの主中にある。その流れは米国を席巻した後、確実に欧州に還流しつつあるのだ。
あのパレスチナの痩せたちっぽけな土地を確保する、あるいはせいぜい中東地域での覇権を確保する、などといった目でシオニズムとイスラエルを見ていると、とんでもない間違いを犯すことになるだろう。彼らの本体は、もし現在のイスラエルが不要になれば巨大な中東戦争を演出することでイスラエルを消滅させ、再びユダヤ人の大虐殺を引き起こすことすら厭わないだろう。彼らにとっては世界支配の意思があるのみでありすべては方便の世界なのだ。これこそ人類最大の悪夢、最大の狂気に他ならない。
次回はこのシリーズの最終回としてこの10回の連作をまとめ、日本で今までほとんど紹介されることのなかったジャボチンスキーとユダヤ・ファシストの流れについて、その悪夢と狂気を表にさらすことによって、イスラエルの暗黒の源流を確認してみることにしたい。
(イスラエル:暗黒の源流 ジャボチンスキーとユダヤ・ファシズム 目次に戻る) (アーカイブ目次に戻る)
【以上、参照資料】
http://www.the7thfire.com/new_world_order/illuminati/Henry_Makow/jewish_conspiracy_is_british_imperialism.htm
第11部 悪魔の選民主義 (2008年10月)
小見出し [「偽メシア」の系譜と近代シオニズム] [神は死に、悪魔が神となる] [シオニズムはユダヤ民族主義ではなく] [暗黒の海に浮かぶ島、イスラエル]
[「偽メシア」の系譜と近代シオニズム]
前回、私は17世紀トルコのサバタイ・ゼヴィ、そして19世紀ポーランド・ドイツのジャコブ・フランクという二人の「偽メシア」をご紹介した。しかし、当然だがこの二人はユダヤ=キリスト教社会に深く根を下ろす「メシア待望」を象徴しているに過ぎず、その背後には「迫害の後にユダヤ人を選民として救済するメシア」という旧約聖書以来の「復讐のメシア」待望がある。また一方でそれを取り巻くキリスト教社会には「千年王国の到来を告げる偽メシアの登場と大迫害」および「キリストの復活=選民としてのキリスト教徒の救済」を願う倒錯したキリスト教徒の「黙示録信奉」が幅広くそして根強く横たわっている。
それは、日ごろは彼らの集団的な深層意識の中に埋まりこんでいるが、それがカリスマ性を持つ人物の言動や現実的な脅威を前にした扇動によって、もはや逃れることのできぬほどに強力な集団的意識を作り上げることになる。これは決して馬鹿げた迷信として無視すべきものではなく、理性や客観性を越えて内側から有無を言わさず人間とその集団を動かす、まさに現実的な力なのだ。
「サバティアン」たちはトルコを根城とし東欧のユダヤ人たちを「選民思想」と「復讐のメシア」願望でまとめていった。そしてそれは欧州各国に広がるユダヤ人連絡網を通してたちまちのうちに広がり、各国で支配者の庇護の下で経済面での特権的地位を確保しその反動として常に非ユダヤ人民衆からの憎しみと攻撃にさらされていたユダヤ人社会の中で着実に根を下ろしていった。それは特に、16世紀から17世紀にかけて最盛期を向かえ18世紀以降衰退していくポーランド=リトアニア連合の中で最も強力な形を取っていったのである。この地域のユダヤ人たちが絶対王権と結び付いて確保していた特権的地位喪失の危機にさらされた18世紀に登場するのが「フランキスト」の動きである。「メシアの登場」によって裏付けられた「選ばれた者たち」の反道徳主義は、喪失への恐怖と非ユダヤ人に対する憎悪に囚われ特権奪回を願望する一部のユダヤ人たちの思考と行動を支配していった。
そしてそれは確実にロシア、ウクライナまでを含む東欧に広がっていったのだ。ウラジミール・ジャボチンスキー、メナヘム・ベギン、イツァーク・シャミール、ダヴィッド・ベン・グリオン、ゴルダ・メイア等々といった「イスラエル建国の祖」たちが、「左右」の違いにもかかわらず、ことごとくこの地域出身者であることに否が応でも気付かされざるを得ない。そして「メシア」ジャコブ・フランクを経済的に支えたのがフランクフルトのロスチャイルド家であり、ここでこの「選民思想=復讐のメシア待望」が「貨幣神」と出会うこととなった。
以来、ロンドンとパリの「貨幣神」は「選民思想=復讐のメシア待望」に取り付かれる者達の守護神となっていくのである。近代シオニズムがこのような歴史の中で徐々に形を取っていくことになる。単なる「選民思想=復讐のメシア願望」だけでは一部の風変わりな集団的狂気で終わるだろうが、そこに現実の世界を強力に動かし作り変えていく「貨幣神」の働きが加わることで、それは資本主義によって動かされる政治思潮の、最も先鋭化され、最も残虐で、最も堅固な動きを作っていくことになる。
そういえば、パリのロスチャイルド家に支えられたフランスの大統領サルコジがトルコ出身のユダヤ人の血を受けている。トルコが「サバティアン」の本拠地だったことを考えれば、彼とネオコン・シオニストとの関係も無理からぬところがある。またサルコジが最も信頼する人物の一人でコルシカ・マフィアのボスであるシャルル・パスカが世界ユダヤ人会議会長で大富豪であるエドガー・ブロンフマンと血縁関係を結んでいることからも、「選民の血統」と「貨幣神」との一体化は覆い隠すべくも無い。そして米国ネオコンやCIAに担ぎ出されフランスのシオニストと一体化している面ばかりではなく、その平然と裏社会を支援する政治姿勢や下劣な品格、堕落した私生活を貫く徹底した反道徳主義を見るときに、サルコジのシオニストとしてのあり方がどこに根ざしどこに向けられているのか、よくわかるはずである。
しかし問題をもう少し広い目で見るならば、現代シオニズムを考える際のポイントはもはや「血の問題」などではなく権力と経済支配への意思に貫かれる「選ばれた者」のための社会作りであると言えるだろう。そこではもはや人種的に「ユダヤ系」であるのかどうかなどは問題にもならないであろう。紛れも無いシオニストであるイタリアのベルルスコーニを見るがよい。米国民主党オバマ大統領候補(2008年11月1日現在)、および彼が指名した副大統領候補ジョセフ・バイデンを見るがよい。
ここで近代〜現代シオニズムの持つもう一つの顔を見ておかねばならない。「イスラエル建国」に尽くしイスラエルの利権を維持し拡大しようとする「狭義のシオニスト」と表裏一体の関係にある、「広義のシオニスト」といえる者達の存在だ。欧米各国には固くイスラエルを支持しイスラエルの利益のために体を張って働く者達(ユダヤ人、非ユダヤ人に関わらず)がいる。しかし彼らはそれほどに《イスラエルを愛している》のだろうか? 確かにイスラエルの「二重国籍」を持つ者は多い。しかし彼らは決してその国に移り住もうとはしない。彼らの多くは欧米各国で支配的な階級に属する者達、銀行や企業を所有して巨額の資本を操り、メディアを所有して情報を操り、アカデミーを支配して論理を操り、法律に精通して法体系を操る者達である。
狭義の「シオニズム」がパレスチナの痩せこけた土地に固執する一部ユダヤ人の偏執狂的な運動であるにもかかわらず、広義の「シオニズム」は資本主義の別名とすら言える。それはもはや人種概念ではなく資本主義によって作られる「選民」を「新ユダヤ人」とする世界支配への願望なのだ。この二つの「シオニズム」は実に上手に結び付けられ、また使い分けられてきた。しかし「貨幣神」を奉る広義の「シオニズム」がその本体
であることに疑いの余地は無かろう。
我々は、いかにジャボチンスキーを追いベン・グリオンを追ったとしても、単に彼らの「イスラエル建国」という政治上の事件ばかりに注目するのでは、実際には何一つシオニズムに関する真実を見極めることはできまい。アメリカ合衆国がどうしていともたやすく最大のシオニスト国家となってしまったのかの理由がここにあるのだ。前回も申し上げたとおり、近代資本主義の土壌ともなった清教徒たちの集団は奇妙な終末思想に取り付かれ、彼らにとってアメリカ大陸こそが「聖なるシオン」に他ならなかったのである。そして資本主義の「祖国」イギリスと近代国家思想発祥の地フランスはともに紛れも無く近代シオニズムの「祖国」でもある。
【以上、参照資料】
http://members.aol.com/ThorsProvoni/C__Judonia1.pdf
http://www.voltairenet.org/article157821.html
[神は死に、悪魔が神となる]
近代シオニズムの大きな特徴としてその無神論が挙げられる。テオドル・ヘルツルを筆頭とし「イスラエル建国の祖」達の誰一人として敬虔なユダヤ教徒はいない。当然だがあの「偽メシア」どもは真っ先に彼らの神を捨てた。彼らはあらゆる道徳的基準を放棄し、自らを「選民」として支配的な地位に付かせるものであればいかなるものをも利用しいかなる嘘をも正当化する。それが彼らの「道徳」なのだ。ジャボチンスキーが言うとおりである。「聖なるシオン」を我が物にするシオニズムこそが彼らの唯一の道徳である。それ以外に道徳など存在しないのだ。
近代シオニズムに関しては、「神を捨てた」と言うよりは「神を取り替えた」と言ったほうが良いのかもしれない。彼らは強力な「貨幣神」の力に従っている。しかし貨幣そのものには善も悪もあるまい。それが選民思想と結び付くときに強力な「悪魔主義」へと変身する。貨幣を支配する者が「選民」として世界を支配するときにその「貨幣神」は巨大な悪魔へと変貌するだろう。
それは、あれこれの理屈ではなく、20世紀の歴史、特に後半に登場したネオ・リベラル経済による世界支配を一見すればすぐに理解できる話である。現在の日本を見てみるがよい。伝統的な独自の民族主義に基づく資本主義解釈はすでに破壊され、徐々にごく少数の「エリート」と大多数の「非エリート」が形成されつつある。「非エリート」たちは若者も老人も食うや食わずに追い詰められしぼりとられる。その分の富と力が《消滅》したわけも無い。単にどこかに集中しただけの話だ。
資本主義の大本山であるアメリカを見るがよい。元来からデタラメな投資に過ぎないサブプライムローンが破綻することは最初から見えていたはずだ。そしてその損失の補填は国民から搾り取った税金でおこなわれる。そしてそれがほとんど何の反対も無く当然のようにおこなわれる。対外戦争政策のたびに税金から膨大な富が軍産複合隊とそれを支える金融機関に流れてきた歴史については言うまでもあるまい。その中で殺され傷つき悲惨な生活に追いやられていくのは大多数の「非エリート」たちである。
CIAの政治謀略によってネオリベラル経済がどこよりも先に実現された中南米を見てみるがよい。中間の階層は経済破綻のたびに次々と薄くなり「エリート」と「非エリート」の2極分化が進んできた。そしてその経済を中心になって作り支えてきたのが紛れも無いユダヤ系のシオニストたちであり、そしてそれと一体化した統一教会などの犯罪者集団、反共に凝り固まるカトリック教会、そしてその背後にいるウオールストリートの富豪投資家どもなのだ。
この二重のシオニズムの構造を正しく読み取っておかねばならないだろう。この大富豪どもとその手先がヒトラーを育て、彼が欧州から一般ユダヤ人を狩りたてパレスチナの地に一部のユダヤ人を集めていったのは、それが彼らの意図する「聖なるシオン=地球全体」を目指す彼らなりの「革命」にとって欠かすことのできないステップだからである。彼らの世界観は資本主義のそれであると同時に特殊な神話の様相を帯びる。彼らは人間の弱さと愚かさと残虐さを熟知しており、人間とその集団が決して冷徹な計算や理屈だけで動きまとまるものではないことを十分に知っている。支配する側にとっても支配される側にとっても、人間にはある種の神話が必要なのだ。
あの無神論者どもが図らずも語る「約束の地」「神の約束」は伝統的なユダヤ教に背を向けて語られたものでしかない。トーラーに書かれた教えを守る敬虔なユダヤ教徒たちは「神の許しがあるまでは決してパレスチナに戻ってはならない」と信じていた。そして居住するそれぞれの国の制度と習慣に順応した生活を「良し」としていたのである。シオニストたちはまずその神を捨てた。次にパレスチナへの「帰還」という神話を徐々に根付かせていった。それは「2000年前に住んでいた場所に戻る権利がある」というものであり、あらゆる合理的な精神を超越した一つの神話体系にのっとったものである。それが本当ならばケルト人たちはイングランドを占領する権利を持ち、アメリカ原住民達はアングロサクソンをワシントンやニューヨークから追い出す権利があることになる。しかしそれはユダヤ人にだけ与えられた絶対的な権利である。彼らは「特別の民」だったのだ。いったい誰によって「選ばれた」?
それにしても奇妙なことだ。すでに数多くのユダヤ人たちが欧州や米国での恵まれた生活を享受していたのである。ポグロムのような迫害があったとしても、もし現実的な利益を考えるのならば、他の国ではなくわざわざすでにアラブ人たちが生活している砂漠の国に移住しようなどと、誰が考えるのか? しかも多くのユダヤ教徒たちにとってそれは神の命令への反逆に他ならない。
シオニストたちはユダヤ教からその「選民主義」と「復讐のメシア」という概念だけを抜き取って利用した。またそれは米国に渡ったプロテスタント達にとっても違和感のあるものではなかった。ヨハネの黙示録に取り付かれた彼らは反キリストの登場とキリストの復活、そして《新たなエルサレム》を信じる。その天国の住民達は《真(新)のユダヤ人》に他ならないのである。黙示録では迫害を受け被害者となったキリスト教徒たちが復讐を神に願うシーンが描かれる。「選ばれた民」が「迫害による犠牲」を経て神話的な力による「聖なる復讐」の結果を享受するというパターンが脳裏に染み込んでいるのだ。しかも最初に「救済の約束」を受けるのは「14万4千人のユダヤ人」である。
それは後に「第2バチカン公会議」を演出するバチカン内の勢力
にとっても実に自然なことであった。ジャコブ・フランクの徒たちがキリスト教各派にもぐりこんでいたことは周知の事実である。こういった「選民主義」と「復讐のメシア」にのっとった神話体系は、欧米の有力な階層の者達を引き付け抵抗感をなくし支持を取り付けるのには絶好のものであった。
こうして、この神話の登場人物となり神話を現実のものとすべく、自らその神話に取り付かれた狭義のシオニストたちがユダヤ人の中から輩出することとなった。一方で広義のシオニストたちはその神話を完成させるべくユダヤ人に対する大迫害を演じる一大役者を育成しその役を演じさせた。今回までに申し上げたとおりである。当然だが、イスラエルという国は、単に中東地域に打たれた欧米資本のクサビであるばかりではなく、膨大な量の資金洗浄の場でもあり、また米国国民から巻き上げた税金のばら撒き場所・たかり場所でもある実に都合の良い場なのだ。
[シオニズムはユダヤ民族主義ではなく]
ネオコンについて少しまとめてみよう。ネオコンは主にレーガン政権の反共政策の中で頭角を現してきたのだが、その少し前にメナヘム・ベギンが歴代の「左翼政権」に代わって指導者となった。そしてその後を継いだのがイツァーク・シャミールだった。もちろん彼らはユダヤ・ファシスト、ウラジミール・"ゼエヴ"・ジャボチンスキーの直系であった。ネオコンの一部は元左翼(トロツキスト)と言われるが、「教祖」とも見なされるレオ・シュトラウスはかつてジャボチンスキー支持者の一人でありナチスの人脈にもつながる人物である。そしてネオコン主流を形作ったポール・ウォルフォヴィッツ、ダグラス・ファイス、リチャード・パール、チャールズ・フェアバンクスなどはことごとくイスラエル「右派」との太い人脈を保ち、米国の国家機密を平然とイスラエルに流す者達だった。またダグラス・ファイスの父親ダルック・ファイスはベギンやシャミールが所属したポーランド・ベタールの一員であった。ネオコンはジャボチンスキー直系のイスラエル「右派」米国出張所と言っても言い過ぎではあるまい。
それではこのネオコン台頭以前はアメリカ合衆国の内部でシオニストが力を持っていなかったのだろうか。とんでもない! 1967年に米国の情報船USSリバティーがイスラエル空軍の爆撃に遭って危うく撃沈されそうになったときに、カンカンになって怒っていた大統領ジョンソンを1日で黙らせたのは何の勢力なのか? そもそも「イスラエル建国」前に米国内ユダヤ人たちによるパレスチナ・シオニストへの武器密輸を黙認させたのは何の勢力なのか? スターリンのソ連と共にあのデタラメなイスラエル建国を断固として支持させたのは何の勢力なのか?
米合衆国のエスタブリッシュメントたちはその始めから広義のシオニストなのである
。彼らは確かに資本を代表している。しかし資本だけではその人間としての姿が存在しない。貨幣そのものは善でも悪でもなく何の意志も持っていない。それに何らかの性格を与えるのはやはり人間なのだ。「貨幣神」は、強烈な世界支配への意思、ある「選ばれた者達の天国」を地球上に実現させようとする強烈な意思と結び付いたときに、その悪魔性を発揮するのだ。それはまさに悪魔そのものである。神はもういない。しかし悪魔はその力をますます発揮しつつある。
近代〜現代シオニズムはもはやユダヤ民族主義ではない。それは「選民」による資本主義経済に基づいた世界の全面支配を目指すものであり、ユダヤのメシア思想と同時にキリスト教の千年王国思想にも根を下ろす、資本主義エリート達による「永遠の天国」実現への動きである。そしてそれは人類の大部分にとっては「永遠の地獄」の実現でしかない。「イスラエル建国」はそのための重要な布石ではあっても、現代シオニストたちの目はパレスチナのやせこけたちっぽけな土地などには向けられていないのだ。再度言うが、彼ら現代シオニストにとって「聖なるシオン」はパレスチナではない。それは《全地球》なのだ。まさに黙示録の世界である。
[暗黒の海に浮かぶ島、イスラエル]
レオ・シュトラウスが将来の「理想社会」を描いて見せるとき、それは哲学者(道徳律を持たない理論のコントローラー)をトップとし政治家と宗教家をその手足として、各国に備えられたメディアと暴力装置を操りながら戦争と平和の幻想を演出して「雲の下にある永遠の地獄」を維持し、それによって「雲の上の天国」を恒久的に維持する世界として現れる。彼が、ギリシャ哲学を語ってカモフラージュしているのだが、バラモンを最上級カーストとして2千年以上にわたって維持されてきたインドのカースト制をイメージしていることは明白であろう。
しかしシュトラウスは一つの大きな嘘をついている。いったい誰がその哲学者達にメシを食わせるのか? 誰が彼らに権威とその地位を与えるのか? 彼はその「神」の名を語らなかった。というよりは語ることを許されていなかったのだ。彼の思想はその弟子であるネオコンの運動の基本理念となったのだが、彼らはその「神」の名を十分に知っている。彼らはその政治代表部として「神」に仕える。それは「人間の顔を持つ資本」であり、人間の持つ魔性を最大限に引き出し具現化したものである。それは虚構そのもの、貪欲さそのもの、そして残虐性そのものである。
20世紀の後半に、一つの巨大な虚構として登場し、選ばれざりし者達(具体的にはパレスチナ人)への残虐の権化として登場し、米国国民の富を無限に吸い取る貪欲さの権化として登場したイスラエル国家は、この「人間の顔を持つ資本」が作る暗黒の海に浮かぶ「島」である。その「神」は、全地球を《聖なるシオン》と変える際に、もしこの「島」が不必要となれば、再び人種的な意味のユダヤ人に対する大虐殺を演出することによって沈めてしまうことすら厭わないだろう。そしてそれは新たな神話の最も重要なイベントとなる。永遠の地獄と永遠の天国を維持するためには強烈に人間の心を支配する神話がどうしても必要なのだ。
ウラジミール・ジャボチンスキーはその神話作りの中心人物の一人として登場した。彼自身はこころざし半ばにして死亡したがその「偽メシア」の系譜は確実に近代世界最大の虚構を築き上げていった。彼は「二重のシオニズム」が持つ一つの顔を代表していたのである。そして彼の「ユダヤ・ファシズム」がパレスチナの小さな土地ではなく世界に広がっていくときに、そのもう一つの顔がその最も獰猛な顔をむき出してくることだろう。
いや、もうすでに顔を見せ始めている。世界に憎しみと復讐心と恐怖をばら撒き、似非科学と反理性主義をばら撒き、それによって人心を支配し政治を支配し、世界の大多数の住民を地獄に閉じ込めて「選民の天国」を永遠に維持しようとするファシストの姿、まさにマイケル・レディーンの言うユニバーサル・ファシズムの姿である。
「イスラエルの源流」探索は決して過去の歴史探訪ではない。それは極めて現在的であり近未来的な問題と直結するものである。「イスラエルの源流」の暗黒はまさしく現代の暗黒であろう。そしてまた、残念ながら非エリートである大部分の我々にとって、未来の暗黒に他ならない。(了)
(イスラエル:暗黒の源流 ジャボチンスキーとユダヤ・ファシズム 目次に戻る) (アーカイブ目次に戻る)